腎症と尿中アルブミン
No.16
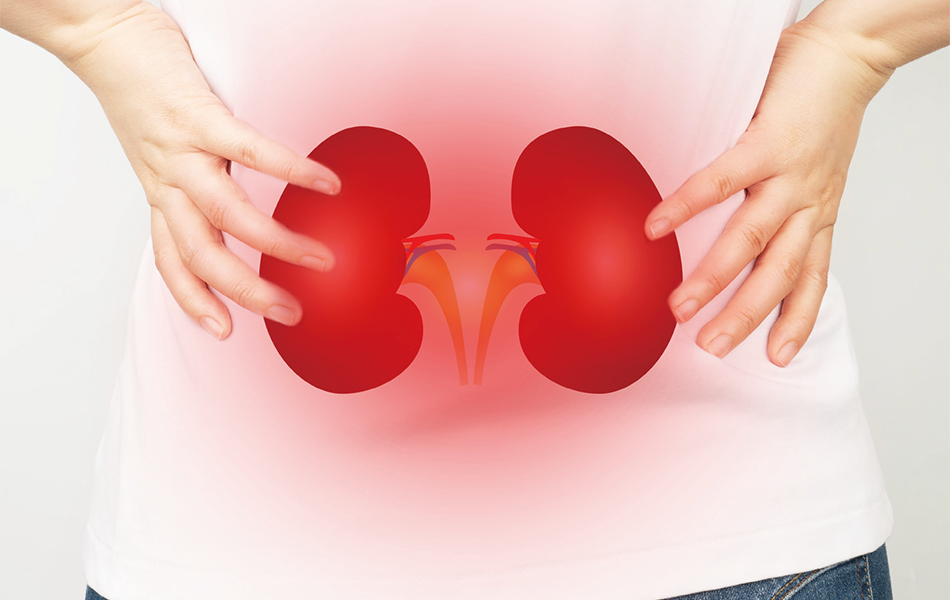
糖尿病のある方にとって、「尿中アルブミン」という検査は、糖尿病性腎症を診断する上で必須の指標です。糖尿病性腎症と尿中アルブミンの関係について解説します。
糖尿病性腎症とは
糖尿病性腎症1)は、糖尿病網膜症、糖尿病性神経障害とともに、糖尿病の三大合併症のひとつです。いずれも、高血糖の状態が長く続いたことにより、それぞれ腎臓、網膜、神経が傷んで発症します。
腎臓には、毛細血管が集まった糸球体という組織があり、血液は糸球体を通過する間にろ過され、体に必要なたんぱく質などは血液中に残し、老廃物と余分な水分や電解質は尿として排出する機能があります(図1)。
糖尿病のある方で高血糖値が続くと、糸球体の毛細血管が傷んで、体に必要なたんぱく質が尿に漏れ出すようになり、糖尿病性腎症を発症します。糖尿病性腎症は進行すると慢性腎不全から透析導入にいたることがあります。透析になると生活の質が著しく低下するだけでなく、心臓病などのリスクも高くなります。腎機能の低下を抑え、透析導入にならないようにするには、腎症を早い段階で発見し、早期に治療を開始する必要があります。

腎機能の検査
腎臓の機能は尿検査(尿たんぱく、尿中アルブミンなど)、血液検査(クレアチニン、尿素窒素、推算糸球体ろ過量など)、画像検査(超音波、CT、MRI など)などで調べることができます。
糖尿病性腎症と尿中アルブミン
糖尿病があると、前述のように糖代謝異常や糖尿病の発症早期から高血糖が続くことで、腎臓の細い血管が少しずつ傷み、糸球体の構造の変化が始まっています。それにより、尿たんぱくの定性検査では陰性の時期でも、血液中のアルブミンというたんぱく質が、わずかながら尿中に漏れ出ていることがあります。尿中アルブミンの増加は、糖尿病のある方の腎臓の血管がどのぐらい傷み、糖尿病性腎症を発症または進展しているかを示す重要な指標といえます。尿中たんぱくが陽性になる頃には、既に糖尿病性腎症が進んでいることが示唆されます。残念ながらわが国の糖尿病診療において、微量アルブミンの測定が十分に行われていない現状もありますが、糖尿病のある方にとって糖尿病性腎症の有無や進行を判断する上で必須の検査です。
糖尿病性腎症の病期
糖尿病性腎症は、「透析療法中あるいは腎移植後(第5期)」も含めて、病期2)を5期に分類されています。病期が進行すると尿中アルブミンの増加と腎機能の低下がみられ、一部の方では透析が必要となる末期腎不全に至るという経過をたどります。糖尿病性腎症の判定には尿中アルブミン・クレアチニン比と推算糸球体ろ過量(eGFR)を用います。
尿中アルブミン・クレアチニン比(mg/g)=尿中アルブミン濃度(mg/L)÷ 尿中クレアチニン濃度(g/L)
推算糸球体ろ過量(eGFR)は性別により算出式が異なります。
男性:eGFR(mL/分/1.73m2)=194×血清クレアチニン(mg/dL)-1.094×年齢(歳)- 0.287
女性:eGFR(mL/分/1.73m2)=194×血清クレアチニン(mg/dL)-1.094×年齢(歳)- 0.2870.739
糖尿病性腎症の各病期の特徴と対処
・正常アルブミン尿期(第1期)3),4)
尿中アルブミン・クレアチニン比30mg/g未満かつ、eGFR30mL/分/1.73m2以上
正常アルブミン尿期といっても、必ずしも糖尿病性腎症が否定されるわけではありません。それは、糖尿病がある方では、高血糖により腎臓の糸球体血管が傷み始めていて、糖尿病性腎症の予備軍の可能性があるからです。1年間に1~2回は尿中アルブミンの検査を行い、尿中アルブミンが増えていないか確認する必要があります。また、しっかり血糖値の管理を行うだけでなく、130/80 mmHg を目標値とした血圧の管理も、糖尿病性腎症の発症を防ぐために重要です。
・ 微量アルブミン尿期(第2期)3),4)
尿中アルブミン・クレアチニン比30~299mg/gかつ、eGFR30mL/分/1.73m2以上
微量アルブミン尿が確認された場合は、3ヵ月後に再検査を行い、微量アルブミン尿期であることを確認する必要があります。微量アルブミン尿期では、病期を進行させないだけでなく、尿中アルブミン量を減らすように、生活習慣の改善や薬物療法も含めた糖尿病の治療に取り組む必要があります。血糖値と血圧に加えて、脂質の管理もしっかり行い、たばこを吸う方は禁煙するようにします。
・顕性アルブミン尿期(第3期)3),4)
尿中アルブミン・クレアチニン比300mg/g以上かつ、eGFR 30mL/分/1.73m2以上
顕性アルブミン尿期になると、急速に腎機能が低下し透析導入に至る方が増えてくるため注意が必要です。顕性アルブミン尿期の方の約6割が、25年以内に透析導入に至るという報告もあります3)。顕性アルブミン尿期以降では、血圧を管理することが最も重要で、必要に応じて降圧薬を使用し、減塩食や運動習慣など生活習慣の改善に、しっかり取り組むようにします。
・GFR 高度低下・末期腎不全期(第4期)3),4)
尿中アルブミン・クレアチニン比は問わず、eGFR 30mL/分/1.73m² 未満
この病期の方で尿中アルブミン量が少ない場合には、糖尿病性腎症以外の腎臓病の場合もありますので、その鑑別が必要になります。この病期になると、25年以内に透析導入に至る方は、約8割に上ると報告されています3)。腎機能低下を少しでも抑えながら、透析導入に対する準備も念頭に入れる時期となります。

糖尿病性腎症と新規透析導入
2021年の統計によると、新たに透析療法に至る原疾患の約4割が糖尿病性腎症で、1998年以降、原疾患の第1位が続いています。2009年をピークに横ばいが続いていましたが、近年ではやや減少傾向となっています5)。これは、糖尿病性腎症の早期発見、早期治療に対する取り組みが進められていることや、有効な治療法や治療薬の開発が進んできたことによると考えられています。糖尿病のある方は、透析導入に至らないために、生活習慣の改善と糖尿病の治療を続けて腎症の進行を抑えることが大切です。

1)日本糖尿病学会 編・著:糖尿病治療ガイド2022-2023 85-89, 2022 文光堂
2)糖尿病性腎症合同委員会・糖尿病性腎症病期分類改訂ワーキンググループ:糖尿病66(11). 797-805, 2023
3)馬場園哲也:Prog. Med. 43(2). 111-117, 2023
4)馬場園哲也:腎と透析94(4). 582-589, 2023
5)花房規男 他:透析会誌 55(12). 665-723, 2022
馬場園 哲也(ばばぞの てつや)
東京女子医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝内科学
教授・基幹分野長
監修 [ごあいさつ]
東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学
教授・基幹分野長
馬場園哲也
編集協力
大屋純子、小林浩子、中神朋子、花井豪、三浦順之助、柳澤慶香
アイウエオ順
※ご所属・役職名は監修・取材当時のものです。
JP25DI00144
